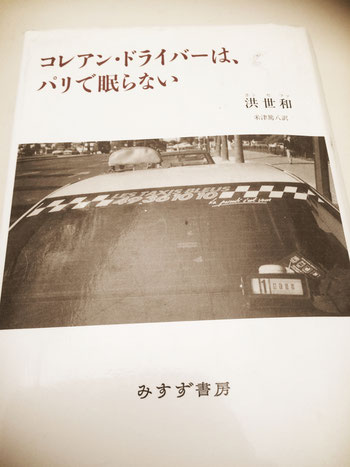
もう一冊、別の友人(かなり年上の友人)がくれた本を読み終えた。洪世和の『コレアン・ドライバーはパリで眠らない』。
偶然にしては出来すぎているようだが、この本もやはり主に冷戦期、南北朝鮮の分裂について書かれている。著者は学生時代の政治運動によって、フランスへの亡命を余儀なくされ、結果として故郷を失ってしまったタクシードライバーである。パリでのタクシー業の苦境や日常的なエッセイから垣間見えるのは、「人間的であるとはどういうことか」、という問いである。
近藤氏の二冊がルポルタージュであったのに対し、この本はどちらかといえば私小説に近い。読者は細かい歴史的事実というよりも、著者の目線にしたがって、彼の感情の起伏を負っていくことになる。とくに、パリで出会うさまざまな「人種」に対する彼の反応は繊細だ。ユダヤ人、アラブ人、韓国人、日本人、ベトナム人、そしてもちろんフランス人。著者の主張は、人間を人種や国籍によって区別するべきだということではなく、それぞれの同一性を持った者たちがいかにして人間的であるかを知るべきだということにある。
彼の政治運動が正しかったのかどうかは僕には判断することができない。「朝鮮」が南北に分裂してしまったことへの悲しみを、僕は永遠に共有することができない。なぜならそれは自分の生きた場所、時代ではないからだ。だがその「証言」に、今この場所で耳を傾けることができたのを幸運に思う。
しばらく前に知り合った韓国系のフランス人が、今まで二か月くらいしか韓国に行ったことがないと言っていたのを思い出す。彼の両親は韓国人だが、かつて西ドイツへの移民であり、炭鉱労働者だったそうだ。韓国には帰る場所がない、故郷はフランスだ、と彼が言っていたのが印象的だった。
この本は、三分の一くらいが政治的な本だったのだが、本質的なのはむしろ「洪世和」という青年の目から見た「もう一つの社会」との出会いの方だろう。彼が何度も強調する「もう一つの社会」とは、フランスであると同時に、フランスから見た韓国のことなのだ。

コメントをお書きください